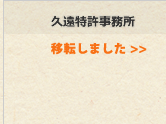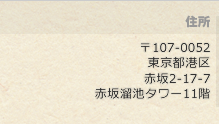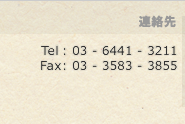連邦最高裁が仕掛ける米国特許訴訟の大変革
2007年11月
![]()
奥山尚一
近年、米国の連邦最高裁は、特許事件を多く取り上げている。2002年の出願経過禁反言に関するFesto 判決は既に旧聞に属するが、今年に入ってからも1月のMedImmune判決、4月のMicrosoft判決とKSR判決など、積極的に特許事件を取り上げており、そのような判決によって、特許訴訟のやり方はここ2年ほどで根本的に覆されたといってもいい。特許訴訟以外の分野でも連邦最高裁が積極的に先例あるいは法解釈を変更する判断をしているところはよく知られている。そのような最高裁の判決の影響を受けて、特許事件の最高裁の役割を果たすために設立された連邦巡回控訴裁判所(CAFC)も、その判例を変更しつつある。
また、連邦議会に提出される特許法案が話題にはなるが通過の見込みが立たない状況の下で、あるいは、米国特許商標庁の過激な規則改正案の施行が期限の前日に連邦地裁の仮処分命令により差し止められるというドラマチックな動きをしている一方で、連邦最高裁は静かにそして着実に改革を実行に移している。
あえて詳細は捨象して、そのような動きを俯瞰してみたい。
高くなった差止命令の基準(eBay)
特許の侵害が認定されれば、侵害行為の差止命令はほぼ確実に得られるというのがこれまでの判例であったが、2006年5月15日のeBay v. MercExchange事件の判決で、最高裁はこれを覆した。最高裁は、差止命令の基準は、特許の分野とほかの法分野とでは何も変わらず、エクイティーの考えに基づく一定の要件を満たさない限り、特許侵害が認定されたとしても差止命令は出せないとした。
永久的な差止命令を出すための一定の要件とは、次の4つである。すなわち、① 特許権者が回復不可能な損害を受けている、② 法定の救済ではその損害を補填するのに不十分である、③ 原告と被告の間の苦境のバランスを考慮して、エクイティー上の救済が正当化できる、④ 永久的な差止命令によって公共の利益が害されない、ことである。特許権の侵害が認められても、これらの要件を満たさなければ、永久的な差止命令は出ないことになる。
これにより、特許発明を実施していない特許権者による差止命令の請求は認められにくくなった。やはり企業にとって一番恐ろしいのは、事業が中断される差止命令であり、それが出にくくなれば特許権の力は弱まる。これは、いわゆるトロールの問題に対する最高裁の一つの回答であると考えられる。
進歩性の基準の再確認(KSR)
2007年4月30日のKSR判決は、最高裁が自らの先例である1966年のGraham判決を確認するものとして、人口に膾炙されているところである。
これに先だって、CAFCは、Alza v. Mylan判決(2006年9月6日)や、In re Kahn判決(2006年3月22日)などによって、最高裁判決の内容を先取りするように、先行技術文献を組み合わせるためには教示、示唆または動機付けの記載が必要であるとするTSM基準の柔軟な適用が可能だとし、非自明性については後知恵あるいは事後的分析により判断を誤る危険性を強調している。おそらく、CAFCの判事の方々も最高裁の近年の動きに敏感になっている証左ではないであろうか。
より高い故意侵害の基準(InreSeagateTechnology)
In re Seagate判決は、最高裁判決ではなく、2007年8月20日のCAFCの大法廷判決であるが、最近の最高裁判決に鑑みて、CAFCが設定したこれまでのUnderwater Devices判決による故意侵害の基準を、自ら完全に見直して、より高いものとした。
今年6月4日に最高裁が、Safeco判決(消費者の信用情報に関する事件)において、標準的な民事の文脈では「故意」の基準は「無謀な振る舞い」(reckless behavior)にある、としたことが大きな影響を与えている。
CAFCは、全員一致の大法廷の判決において、過去の「故意」の侵害の立証基準を覆し、故意による損害の増額認定には、「少なくとも客観的な無謀さ(objective recklessness)」が明白かつ確信を抱くに足りる証拠 (clear and convincing evidence)によって証明されることを要するとした。この判決によって、これまですべての潜在的侵害者に課されていた「相当の注意を払う積極的義務」がなくなったことになる。つまり侵害が故意によるものであるという認定の可能性は相当程度減ったといえ、「故意」であることを要件とする懲罰的損害賠償の可能性も減った。
この判決により、おそらくは、弁護士が非侵害と判断した正式の鑑定書がないからといって、すぐに侵害行為が故意ということにはならなくなり、鑑定書の必要性は減殺されることになろう。侵害が故意でなければ、現実の損害の三倍を上限とした懲罰的損害賠償の認定を受けることがなくなる。
このことは、侵害が故意であるとの追及を受ける被告にとっては、二重の朗報である。まず、費用のかかる鑑定書を得なくても懲罰的三倍賠償の認定を受ける可能性が減る。そして、弁護士の正式な鑑定書によって、非侵害、特許無効、権利行使不能などが示されていないと、故意侵害と認定される可能性があり、これまではその立証のためにはせっかくの顧客と弁護士の間の守秘特権を放棄しなければならないことがあったが、その危険性が減ろう。
はるかに提起しやすくなった確認訴訟(MedImmune)
特許を侵害していない、あるいは特許が無効であると信じていても、それを確認するための確認訴訟を連邦地裁に提起するには、「現実の紛争」(actual controversy)がなければ訴えの利益がないものとして却下される。したがって、確認訴訟を裁判所に受け付けてもらうためのハードルは高かった。
MedImmune事件(MedImmune v. Genentech)では、Genentechとのライセンス契約があったMedImmuneは、新たに特許になったGenentechの特許権は無効で侵害していないので、追加のライセンス料の支払いは必要がないものと考えた。しかし、ライセンス対象の医薬Synagisは同社の売り上げの80%以上を占める主力製品だった。そこで、MedImmuneは、条件付きでライセンス料を支払い、確認訴訟を提起した。地裁は事物管轄がないとして訴えを却下し、CAFCはそれを維持した。
1969年の最高裁の先例Lear判決(Lear v. Adkins)は、ライセンシーはいつでもロイヤルティの支払いを停止して特許の有効性を争うことができるとしている。しかし、この最高裁判決によっては、ロイヤルティの支払いを継続している場合にどうなるかは明らかではなかった。その後、CAFCは、Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.判決(2004年)により、ライセンシーが自らの意志でライセンス契約をしていて、ライセンス料を支払っている状況では、つまりライセンシーが契約を破棄することなくライセンス契約の利益を享受している状況では、「現実の紛争」があるとはいえないと判断していた。MedImmune事件において、CAFCは自らの先例に従ったのである。
最高裁は、2007年1月9日の判決で、Lear判決の状況に立ち帰って考察を行い、ライセンス契約が破棄あるいは解除されていなくても、その契約にかかる特許の無効の確認を求める訴訟を提起できるとし、本事件のCAFC判決を破棄、差し戻した。
その結果、ライセンシーの側あるいはライセンス交渉を持ちかけられた側からの非侵害あるいは特許無効の確認を求める訴訟の提起が、相当程度容易になった。この判決は、今後、ライセンサーとライセンシーの関係、ライセンス契約の条項などに影響を与えると考えられる。
MedImmune判決を受けた二判決(SanDiskとTeva)
最高裁のMedImmune判決を受けて、CAFCはさらに踏み込んだ判断を下している。
「現実の紛争」があるためには、「訴訟の相当の恐れ」(reasonable apprehension of suit)が求められていたが、2007年3月26日のSanDisk判決(SanDisk v. STMicroelectronics)において、CAFCは、「行っているあるいは行おうとしている他人の特定された行為に対して特許権者が特許権を主張し、その他人がライセンスなしに侵害を構成するとされた行為を行う権利があるとすれば」、訴訟を起こすための憲法第3条の規定を満たす、としている。
Teva判決(Teva Pharma. USA v. Novartis Pharma.)は、薬剤の特許訴訟に関して、同様に、確認訴訟を起こすための基準を下げるものである。
つまり、確認訴訟は従来に比べて遙かに提起しやすくなった。MedImmune最高裁判決を含むこれらの判決は、非侵害と特許無効の両方の確認訴訟に適用されると考えられる。
これは、従来から提案されている第三者が参加しての特許の見直し手続の改善あるいは異議申立手続の全く進まない立法化の問題を、確認訴訟の提起のための基準を下げることで、司法の側面から解決しようとするものであると考えることができる。
IllinoisToolWorks判決とMicrosoft判決
それぞれ2006年3月1日と2007年4月30日のこれらの判決は、その影響は特定の分野に限定されてはいるが、特許の力をより限定的に解釈すべきであるとし、特許権の効力の強さについてより慎重な立場をとるものである。CAFCの判決を覆しており、CAFCのこれまでの基本的な方針に変更を迫っている。
まずIllinois Tool Works事件(Illinois Tool Works v. Independent Ink)であるが、これは、特許製品と非特許製品を強制的に抱き合わせて販売する行為について、特許製品については、市場支配力(market power)があるものと推定される、としていたこれまでの判例を覆したものである。この判決により、抱き合わせ販売が独禁法違反であるというためには、特許権の対象製品に市場支配力があったことを立証しなければならなくなった。結果として、裁判所によるシャーマン法(日本の独禁法に当たる)の解釈と、特許法の規定や政府機関による知財ライセンスガイドラインとの調整が図られることになった。なお、この判決は特許権に関するものであるが、著作権などのその他の知的財産権にも同様に適用できるものであると考えられる。
Microsoft判決(Microsoft v. AT&T)は、米国から送られたソフトウェアが、外国で製造されて外国で販売されるコンピュータに組み込まれた場合、米国特許が適用されないことを確認したものである。マイクロソフトのウィンドウズOSがAT&Tの特許(録音した音声をデジタル的にコード化して圧縮する「装置」に関する)を侵害していると認定された。連邦地裁においては、米国内での侵害に加えて、マスターディスクを海外に運ぶかソフトを送信して、それを海外でコンピュータに組み込んだ製品についても、特許製品の部品を海外での組み立て(combination)のために米国内から許可なく供給することは侵害になるとする特許法271条f項の規定に基づき、マイクロソフトの行為は「部品」の供給に該当するとして、侵害が認められた。CAFCは地裁判決を維持した。
これに対して、連邦最高裁は、特許法271条f項の設置に至る立法の経緯などを考慮して、米国から輸出したのはソフトのインストールされた写し自体ではないので、関連するコンピュータの「部品」には該当しないとした。最高裁は、271条f項の規定は厳密に解釈されるべきであり、ソフトウェアをコピーすることの容易さについては、連邦議会は、Digital Millennium Copyright Actを立法するなど、十分に理解しているので、必要であるなら法改正が行われるべきことを示唆している。
消尽についての最高裁の審理(Quanta)
いったん特許権者またはその承認を得た者が特許製品を市場に置いたならば特許権の効力は消尽しあるいは用い尽くされてしまい、その後その製品を得た者に対しては行使できない、とする特許権の消尽の考え方は、成文法に規定はないものの、特許制度の中で非常に重要な位置を占める概念である。連邦最高裁は、この基本的な問題を取り上げることとした。
Quanta v. LG Electronics事件において、昨年の11月30日に提出された上告受理の申立てに対して、2007年9月25日、最高裁は、審理を行うことを決定した。これに先立って、4月16日には米国政府の訟務長官に意見を求めていたが、8月24日には上告の受理を薦めるブリーフが提出されていた。
審理の対象になるのは、「本裁判所または他の控訴裁判所の判決に反して、被上告人の特許権が、インテルとのライセンス契約と、ライセンスの元での上告人らへのインテルの販売によって消尽していないと判断したことがCAFCの誤りであったかどうか」である。LG Electronicsは特許権をインテルにライセンスしていたが、その条件の一つにインテルは「インテルの製品をインテルのものでない製品と組み合わせて製造する製品には、明示的にも黙示的にも」このライセンスが適用されないことを顧客に知らせることが求められており、インテルはその通知を行っていた。そのため、Wang Laboratories社から買った特許4件と自らの特許1件に基づいて、インテルからチップを買ってパソコンを作っている台湾のQuanta Computerなどの数社を侵害で訴えたものである。
ここで重要になるのは、最高裁のUnivis Lens判決(1924年)とCAFCのMallinckrodt判決(1992年)である。
最高裁のUnivis Lens判決では、「発明を具現化した機械を販売する特許権者は、その機械をその合理的な使用目的のために用いる購入者に対して特許侵害訴訟を提起することはできない」としている。ところが、CAFCのMallinckrodt判決では、ある特許発明製品の「条件付き」の販売によって特許権は消尽しないとしている。当然、CAFCは、Mallinckrodt判決を出す際には先例の最高裁判決を考慮したのではあるが、前提となる事案が違うと判断していた。これに対して、訟務長官は、最高裁判例からの乖離を指摘している。
来年の6月ごろにも最高裁が判決することが期待されている。
まとめ
これまで説明してきたように、最高裁は、CAFCの特許事件における判断に満足していないことは明らかである。その判決の中で、CAFCの判例が最高裁のそれに従っていないことを繰り返し指摘している。そして、CAFCが作り出した特許権の効力をより強める流れを押さえ込もうとしているかのようである。特許権の消尽、永久的差止命令の基準、故意侵害の認定基準といった事項は、特許制度の根幹に関わる基本的な問題であり、それらについて、連邦最高裁の新たな判断が示されたこと、そして、これからも示されていくことは特許訴訟の実務に極めて大きなインパクトを与えつつある。
また、日本には懲罰的損害賠償規定はないが、その他の面で、日本の特許侵害訴訟の基本的な考え方にも影響があるであろう。
(本稿は、「ザ・ローヤーズ」2007年12月号のための原稿に若干手を入れたものです。)
![]()