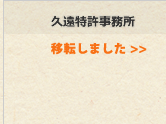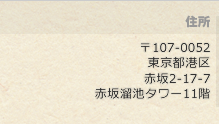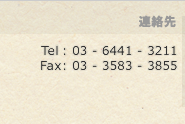塩酸メクロフェノキセート事件
大阪地裁昭和49年7月20日判決
- 侵害
差し止め命令、仮執行なし
大阪高裁昭和52年4月27日判決 - 非侵害
最高裁昭和53年5月1日判決 原判決維持
文責:奥山尚一
※(財)知的財産研究所刊の「特許クレーム解釈の研究」(IIP研究論集4)、1999年6月25日初版発行に収載されている論文である。
![]()
1.はじめに
この事件では、物質特許が許されていなかった時代の新薬の製法特許に対する均等論の適用が論点となった。第一審判決では、均等論が適用されて、侵害があったと判断されたが、第二審においてこれが覆され、非侵害との判断がなされた。最高裁判所は、第二審判決を維持した。
この事件を特徴づけているのは、係争の対象となった特許が、新規化合物である医薬品の製法特許に関していることである。この事件の当時、物質特許は特許法32条において禁止されており、新規な化合物について保護を受けようとすれば、その製法について特許を受けるほかはなかった。実際本件特許についても、直接の特許保護の対象となった製法自体には進歩性はなかったものと考えてよい。特許請求の範囲に記載された化学反応は、優先日当時、有機化学の分野で広く行われていたエステル化の手法を用いたものであり、目的化合物をにらんだ出発物質成分の特定を除けば、方法としては新規性はないものといえる。しかし、その方法により生成される化合物の新規性とそれが有する予測し得ない効果を方法自体の効果であるとみなして、公知の方法に類似した方法に特許が付与されたものである。いわゆる「化学的類似方法の特許」といわれるものである。
したがって、本件の出願時においては、真の保護対象であるべき新規化合物に対して直接的な保護を受けることはできなかった。化学会社や医薬会社は、新規で有用な物質の開発に多大の投資と年月をかける。商品となるのは、多くの場合、物質である。製法自体の開発のために努力するわけではない。しかし、直接的な保護の対象となるのは、製法であった。新規な化合物に与えられる保護も、製法に対する特許による間接的なものに成らざるを得なかった。
それが問題であるのは、ある化学物質があるとして、それを製造する方法は、通常一つではないことである。明細書にありとあらゆる製造方法を記載し、それをクレームすることは、およそ現実的でなく、また、公開された明細書を見て、そこに記載されていない製法を考えつくことは、新規化合物の開発の困難性に比べれば、非常に容易であると言わざるを得ない。
このような状況において、均等論の適用が盛んに議論されていた。(1)
なお、当時の新薬特許の多くがそうであったように、本件の特許権者も外国籍(フランス国籍)であった。
2.事案の概要
2.1 特許発明の技術的内容
訂正審判の結果訂正された請求の範囲の文言に基づいて模式化して表すと、特許発明(特許第413190号)は、下記の反応式によって下記目的化合物を製造する方法である。
特定の媒質中で、
A + B → C (a1法及びa2法)
C + D → 目的化合物
または、
A' + B' → C (b法)
C + D → 目的化合物
という化学反応を行う。
ここで、
| A | : | 一般式RCOOHで表される酸のハロゲン化物1モル (Rは、クロルフェノキシメチルまたはアルキルクロルフェノキシメチル) |
| A' | : | 上記酸の遊離酸(ClやBrなどのハロゲンがついていない点でAと異なる) |
| B | : | アミノアルコール又はアミノチオール1又は2モル(a1法及びa2法) |
| B' | : | 前記アミノアルコールまたはアミノチオールに相当するハロゲン化アミン (ClやBrなどのハロゲンがついている点でBと異なる)(b法) |
| C | : | 反応生成物 |
| D | : | 所望の酸類またはハロアルキル(オプショナル) |
| 特定媒質 | : | 無水有機媒質 |
そして、目的化合物は、
一般式
| R' | |
| R-CO-X-A-N< | |
| R" |
(但し、Rは上記と同様の基、Xは酸素または硫黄原子、Aは側鎖または直鎖を有する2価の炭化水素基、R'及びR"は水素原子またはそれぞれが同一かまたは異なる不飽和または飽和の脂肪族、芳香族または複素環の1価残基または同時にヘテロ原子またはヘテロ原子を持っていない2価の残基または1価残基もしくは水素原子及びA基と環状鎖を形成する2価残基を示す)により表される新規な塩基性エステル類および該エステルと酸類または第4級無毒ハロゲン化アルキル化剤との付加塩である。
なお、かっこ内にa1法、a2法、b法とあるのは、特許請求の範囲の記載に技術的考察を加え3法に整理したもので、大阪地裁および大阪高裁の判決文において説明されているとおりである。
この目的化合物は、動物組織の中枢神経系に及ぼす刺激作用を有し、中枢神経刺激作用、意識障害(昏睡)の回復作用、視床下部・脳下垂体分泌刺激作用の薬効を有する。
2.2 侵害品
特許権を侵害して製造されたとされた化合物は、メクロフェノキセートと呼ばれ、上記目的化合物の一般式において、RがP-クロルフェノキシメチル基、Xは酸素、Aはエチレン基、R'とR"をいずれもメチル基として選んだ物質である。その塩酸塩が塩酸メクロフェノキセートである。
つまり、侵害品とされた化合物は、明らかに、特許発明の目的化合物に包含されるものである。
また、被告は、塩酸メクロフェノキセートを製造し、これを錠剤および注射剤として製剤の上、これに「プロセリール」なる商品名を付して、販売等の行為を行っていた。
2.3 イ号方法
判決に添付された別紙目録によれば、イ号方法は、「P-クロルフェノキシ酢酸とβ-ジメチルアミノエタノールとを、無水操作を施さないキシレン中で、反応によって生成する水を連続的に分離しながら反応せしめ、次いで塩化水素ガスを吹き込み、塩酸メクロフェノキセートを得る方法」である。
2.4 特許発明とイ号方法の対比
特許発明とイ号方法の特徴を対比して表にすると次のようになる。
|
上記のように、特徴1の解釈はさておき(キシレンは水にほとんど溶けないので、イ号方法も実質的に無水状態で行われるものと考えることもできる)、特徴2が特許発明とイ号方法の間で明らかに異なっており、その結果、文言通りの侵害はないものと考えられる。この点については、第一審、第二審とも判断は同じである。
特許発明とイ号方法の対比をより明らかにするために、目的化合物と、それを得るための各方法における出発物質を以下に対比する。
目的化合物(メクロフェノキセート)
a1,a2法(A+B)
b法(A'+B')
イ号方法(A'+B)
2.5 優先日当時知られていた合成方法
優先日当時知られていた、エステルの合成方法としては、原告がケミカル・アブストラクツを検索して、ジメチルアミノエタノール、ジエチルアミノエタノールの各エステルについて調べたところによると、甲第15号証の1に示された調査結果が得られた。ジメチルアミノエタノールについてのみ、その結果を転記すると次のようになる。
| [ジメチルアミノエタノールのエステルの合成法] | |
| 酸クロライド法(本件特許) | 138件 |
| ハロゲン化アルキルアミン法(本件特許) | 89件 |
| エステル交換法 | 41件 |
| アミノ基置換法 | 25件 |
| カルボン酸法(イ号方法) | 15件 |
| 酸無水物法 | 5件 |
| その他 | 11件 |
| 合計 | 324件 |
つまり、本件特許の製法自体は、ありふれた酸クロライド法、ハロゲン化アルキルアミン法を利用したものである。他方、イ号方法は、最もよく知られた標準的な方法ではなく、あまり用いられていなかった方法を利用したものである。次に説明するように、このカルボン酸法があまり用いられていなかったのには、それなりの理由があり、実際、イ号方法においても、得られる結果は、請求の範囲に記載された標準的な方法よりも劣るものであった。この点は、被告側も認めるところでもあった。
2.6 特許方法とイ号方法の効果の比較
原告、被告とも特許方法とイ号方法の効果の比較をすべく、データを提出しているが、原告側のデータを転載すると、次のようになる。
(1)収率(パラクロルフェノキシ酢酸から)
| a1法 | 88.4~90.0% | |
| a2法 | 88.7~90.4% | |
| イ号方法 | 72.7~75.0% |
(2)所要時間(パラクロルフェノキシ酢酸から)
| a1法 | 6時間 | |
| a2法 | 8時間 | |
| イ号方法 | 11時間 |
(3)操作の困難性 3方法ともになし
2.7 請求項の記載形式と特許性の所以
目的化合物は、優先日当時、新規であった。当時、物質自体をクレームすることは認められていなかった一方、目的とする化合物が新規で、格別な効果を有するものであれば、その生成に用いられる化学反応または製造方法自体は特に目新しいものでなくても、目的化合物の新規性と進歩性に依拠して、目的化合物の製造方法の特許が認められていた(物質特許制度は昭和50年改正法により導入され、昭和51年1月1日に施行された)。
したがって、本件特許においては、物も製法も一つの請求項で限定されている。
なお、判決等において使用される「エステル」とは、有機酸や無機酸とアルコールが脱水反応して得られる化合物、及びこれに相当する構造を持つ化合物の総称として定義されるものであり、「C-O-C」の構造を有する化合物を広く一般的に指す言葉である。
3.各審級における理由要旨
次に各審級においてどのような判断がなされたかを検証するため、理由の要旨を問題点ごとに抜粋、引用してまとめてみる。
3.1 大阪地裁(昭和45年(ワ)第5034号)
(1)本件特許発明の課題と解決
本件特許の発明者は、β-ジメチルアミノエタノールに適当な酸を反応させ新規な塩基性エステルを創製することを課題として研究の末p-クロルフェノキシ酢酸のβ-ジメチルアミノエチルエステル塩酸塩ならびにこれに近似する物質が動物組織の中枢神経系に及ぼす刺激作用を有する点において治療的価値が高いことをつきとめ、右特異な薬効を有する新規物質の製造方法につき、特許請求の範囲に記載の通り構成して特許出願をなし特許を得たものである。
(2)本件特許発明の保護範囲
本件特許発明において、固有の発明的性格が存する新規な点は、特許請求の範囲に記載の酸又はアミノアルコールあるいはアミノチオールの「ハロゲン化」にはなく、専ら右酸又はアミノアルコールあるいはアミノチオールの選定部分にあると認めるべきである。すなわち、R-CO-X-A-NR'R"で現わされる新規エステル類を生成せしめるため、RCOOHで現わされる酸とY-A-NR'R"で現わされるアミノアルコールあるいはアミノチオールを原料成分に選定した点に発明的性格が存すると認めざるを得ない。
そうすると、被告方法は本件特許方法と操作方法を異にするが、本件特許発明の発明的性格が存する新規部分を共通にするものであるというべきである。
本件発明にかかる新規物質を得ることを目的とし、特許方法中これに固有の発明的性格を有する新規部分を共通にし、その余の部分は特許の優先日当時、化学教育を受けた当業者であれば格別研究に値する努力をしなくても、公知の知識、当業者の常識に基づき特許方法から容易に推考し得る範囲の実施形式については、発明者において特許発明とともに、右実施形式も均等の技術として発明を完成していたと認めるのが相当である。したがって、特許公報により、新規な薬効を有する化合物の化学構造、融点等が教示され、その製造方法の実施例について当業者を含む一般に開示がなされるときは、前記の要件を充足するような均等技術についてはたとえ説明がそこまで及んでいなくても、当業者においてそれを推考することが容易である筈であると言うことができるのであるから、右発明の開示は右均等方法をも含めて暗黙裡に教示しているものと解しなければならない。そうすると、出願人において右均等方法につき権利を主張しない旨を表明したこと、その他特許の保護範囲から右均等方法を用いる製法を除外して解釈すべき等特段の事情がない限り、第三者が右均等手段を用いる製法を用いることは特許発明に属する技術を剽窃することに外ならず、これに因り特許権者の権利を害するものといわなければならない。
(3)被告方法と本件特許方法との特許法上の均等
p-クロルフェノキシ酢酸のハロゲン化物に代え、その遊離酸にβ-ジメチルアミノエチルアルコールを反応させても、・・・・・同一の目的物が生成することは明らかなところである。
a1法、a2法も被告方法も均しくβ-ジメチルアミノエタノールが試薬であり、・・・・・共にその置換反応がカルボニル炭素(アシル基)上で生起する求核置換反応であることを推認することができる。
被告方法ならびにその操作条件は、本件特許の公開を前提とすれば、これから一般化学技術者が常識として当然想起するものであり、何等新規性なく、その実施は極めて容易であるとの技術関係を認めることができる。
以上検討したところによれば、被告方法はp-クロルフェノキシ酢酸とβ-ジメチルアミノエタノールを原料として用いるものであるから、特許方法固有の発明的性格が存する新規な部分を共通にするものであり、ただその原料のうちいずれかをハロゲン化物として反応せしめるという特許方法の要件を欠いている点については、その要件に代る手段として反応温度をより高める、脱水方法を用いる等の処理手段を施して特許の目的物に含まれる塩酸メクロフェノキセートの新規物質を得ているのであり、しかも右代替手段の技法は優先日当時当業者に本件特許方法から極めて推考容易な域を出でない事項であると認められるのであるから、被告方法は本件特許方法の「原料のうちいずれかをハロゲン化物とする」との要件につき均等の手段を用いているものと認めるべく、被告の被告方法の実施行為は本件特許権を侵害するものといわなければならない。
3.2 大阪高裁(昭49年(ネ)1450号)
(1)権利範囲
第三者に対する法的安定性との権衡上、その効力の及び範囲は明確に公示されるべきであり、その限りにおいて権利としての保護を受けうるものであると解すべきである。そして、特許発明の技術的範囲したがって権利範囲は、願書に添付した明細書の「請求の範囲」の記載に基づいて定められるのであるから、「請求の範囲」の記載以外のものには原則として排他的効力が及ばないというべきである。特許請求者は、特許権の付与を受けうべき事項はこれを「請求の範囲」に記載して請求することができるのであるから、これを記載しなかったことによる不利益は自ら負担すべきである。ただ、具体的な権利範囲の認定にあたっては、形式的に「請求の範囲」の記載の文字のみに拘泥することなく、その他の記載事項および添付図面の記載をも認定資料として実質的にその範囲を確定すべきものと解する。
・・・・・実験的経過と結果が重視される化学方法の特許にあっては、実験的事実に裏付けされた発明の目的、構成および効果を「発明の詳細な説明」の項に記載し、その構成要件事項を「請求の範囲」の項に記載することを要するものと解される。
(2)技術的思想
本件特許方法は、出発物質の一方としてハロゲン化物を用いることを要件とするものであって、これを用いない控訴人方法とは技術的思想を異にするものと解すべきである。
(3)相互代替性
「実際に具体的なエステルを合成するにつき、いかなるエステル化法によるのが可能であり、かつ工業的製法として耐えうるものであるかは、具体的な実験事実の裏付があってはじめて結論づけることができるもの」というべきであって、目的物がエステルである以上、その製法はすべてのエステル化法が常に相互に代替性を有するものとすることはできないと解すべきである。
(4)置換可能性と容易想到性
本件特許の優先日当時、・・・・・当該エステルであるメクロフェノキセートがカルボン酸法により効率よく製造されうることを知見していたと認められるに足りる実験例などの証拠はなく、また本件特許の明細書にも右事実を推認しうる事項の記載が全くないため、むしろカルボン酸法による製造につき想到し得なかったのではないかと推測することができ、・・・・・本件につきカルボン酸法を採用することは、右塩の生成による収率の低下、長時間の加熱操作の必要、これによる原料および生成物の熱分解の危惧等により極めて不利であると予測される旨述べているのであり、これに前認定事実を合わせ考えるとき、むしろ、a1法、a2法を、これと実質的に同一の作用効果を営むものとして、控訴人方法に置換することが可能であって、しかも本件特許の優先日当時当業者が容易にこれを推考し得たものと認めるには至らないといわざるを得ない。
3.3 最高裁(昭52年(オ)1072号)
原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
4.解説
(1)技術的範囲の認定と均等について
大阪地裁判決は、均等論を原則適用と考えているようである。固有の発明的性格が存する新規な部分は、本件特許では、原料成分の選定にあるとした。そして、イ号方法との差異は、優先日当時、「当業者に本件特許方法から極めて推考容易な域を出でない事項である」と認定した。つまり、特許請求の範囲の記載の要件を発明的性格を有する新規な部分とそうでない部分に分け、この発明的性格を有する新規な部分が共通し、その余の部分は特許の優先日当時、当業者であれば、公知の知識、当業者の常識に基づき特許方法から容易に推考し得る方法は、保護範囲に属するものとしている。
このように「固有の発明的性格が存する新規な部分」を抽出して考えること自体、請求の範囲の記載の文言通りの解釈を越える技術的範囲を前提としたものと考えられる。
また、地裁判決が、「その他特許の保護範囲から右均等方法を用いる製法を除外して解釈すべき等特段の事情がない限り」、均等方法を実施することは、特許権者の権利を害するものといわなければならないとしていることからも(「理由」の項、七の(7))、均等論が原則的に適用されると言う考え方に近いようである。
そして、「均等」という言葉が、判決文の中で頻繁に用いられている。
これに対して、高裁判決においては、技術的範囲は、「請求の範囲」の記載に基づいて定められるもので、「請求の範囲」の記載以外のものには原則として排他的効力は及ばないとした上で、「請求の範囲」にある文字のみに拘泥することはないとした。
ただ、均等物の実施が権利範囲に入りうるか否かについては何も述べておらず、被控訴人の「均等」の主張に答える形で、置換可能性、容易想到性を否定している。
したがって、高裁判決は、形式的にも、均等論適用の可能性を示唆していないものと解される。
(2)技術的思想の把握
技術的思想の把握について、地裁は、新規化合物とその原料成分の選択が重要と考えた。これは、新規化合物の持つ効果ゆえにその製造方法の特許性を認めるという化学的類似方法の特許性の判断基準に近い考え方である。本件特許発明の課題と目的は、有用な新規化合物の発見にあった。その認識に基づいて、特許発明の方法は、イ号方法と同一の技術的思想であると判断された。
これに対し、高裁においては、方法の手順に重きが置かれ、その結果、イ号方法は、特許発明とは技術的思想を異にすると認定された。請求の範囲に記載された「方法」を単にいくつかの手順の集合としてとらえれば、特許方法における手順に発明理解の重きを置くことは、納得がゆくように思える。
しかし、出願の当初には物質特許が認められていなかった一方で、高裁判決が出された時点では物質特許制度はすでに始まっていた。むろん化学的類似方法は、物質特許制度のもとでも、物質自体と同様に特許保護の対象となるものであり、特殊な理論の上に成り立つものではないが(1)、物質特許制度がなかったときと、それが制定された後とを比較すれば、目的化合物の効果ゆえに特許される化学的類似方法の持つ意味は相当異なっている。それは、新規化合物に対する保護を受けるためには、便法として、化学的類似方法の特許を受けざるを得なかった時代と、物質自体が保護されて、それを補完して、あるいはそれに重ねて、化学的類似方法としても保護を受けうる現在との現実の相違である。
上述のように、高裁判決においては、本件特許発明の目的や解決すべき課題に触れることなく、つまり、有用な新規物質を提供するという本件特許発明の本来の目的を全く考慮することなく、本件特許発明を、単なる物の製造方法としてとらえている。物質自体の保護が得られないがために、本件特許が製造方法にかかるものとせざるを得なかったという現実は顧みられていない。このことは、高裁判決が、「実際に具体的なエステルを合成するにつき、いかなるエステル化法によるのが可能であり、かつ工業的製法として耐えうるものであるは、具体的な実験の裏付けがあってはじめて結論づけることができるもの」であるとして、本件特許発明の目的、課題を、イ号方法の工業的な実施の可能性の探求に置き替えていることからも明らかである。
(3)特許発明の課題と解決
地裁判決においては、特定の薬効の効力と持続性を、慣用のエステル化を用いて改良したことを課題と解決として認定している(地裁判決の「理由」の項の「二 本件特許発明の課題と解決」)。
これに対して、高裁判決は、「理由」の項では、目的化合物の効力等には一切触れていない。課題と解決は、もっぱら請求の範囲に記載された化学反応手順にあると考えているように見受けられる。
このような明らかな相違は、上述のような、技術的思想に関する裁判所の態度が異なることから生じている。それはとりもなおさず、科学技術の実体に迫って事案を判断しようとする考え方と、特許請求の範囲の記載に基づいて、恣意性を排除して権利範囲の解釈を行おうとする態度との相違に他ならない。
(4)置換可能性、置換容易性
地裁判決においては、置換可能性あるいは相互代替性について、特に明言の認定はなされていないが、請求の範囲に記載されたハロゲン化物を用いた方法と併せて、イ号方法が優先日当時公知であったとの認定はある。
すなわち、現在通説的に考えられている置換可能性の要件について、地裁は明確な判断を行っていない。これは、「固有の発明的性格が存する新規な部分」が、「特許請求の範囲に記載の酸又はアミノアルコールあるいはアミノチオールの『ハロゲン化』にはなく、もっぱら右酸又はアミノアルコールあるいはアミノチオールの選定部分にあると認めるべきである」としていることに対応しているようである。すなわち、目的化合物がエステル結合で繋がれる二つの構成部分からなるとき、その二つの構成部分が重要なのであって、ハロゲン化法を用いようと、脱水反応によろうと、そこには発明的性格はないとの認定につながる。
地裁は、請求の範囲のエステル化法とイ号方法のエステル化法がそれぞれ慣用されていたことと、発明的性格はエステル化の範囲内での反応機序には見出せないことを認定したに留まる。しかし、容易推考性については、はっきりと認定している。
高裁判決では、反応機構の同一性と、出発物質と操作手順の選択という問題は直接関連がないとされ、優先日当時において種々知られていた「すべてのエステル化法が常に相互に代替性を有するものとすることはできないと解すべき」ことと、イ号方法の実際に不利な点と、不利が予測された点とに基づいて、置換容易性と置換可能性を否定した。この「すべての」エステル化法が「常に相互に」代替性を有するというのも、ひどく厳格な条件で、およそ現実的でない上に、なぜ特許明細書の記載から出発して、置換可能あるいは置換容易であるという論証では不十分であるのかの説明もない。
したがって、地裁判決は、現在通説的に考えられている均等論の要件から見る限りは、若干の問題があるようではあるが、一見通説的均等論に沿ったかのように構成された、高裁の意見も、我々が参考にできる部分は少ないと考える。
(5)物質特許がなかった時代の保護のあり方
地裁判決においては、本件特許発明の「固有の発明的性格が存する新規な点」の認定において、特許法32条2,3号(特許を受けることができない発明)の規定を考慮している。物質特許が許されていなかった出願当時の状況に鑑みて、保護範囲を規定しようとするものである。ハロゲン化物を用いる点が本件特許発明の中核をなす技術的思想であるという被告の主張に対し、地裁は、エステル化におけるハロゲン化物の使用などは優先日当時慣用の方法であったので、そこに固有の発明的性格が存するとはとうてい認めることができないし、原料成分の選定を重視する考え方は、特許法32条の法意にも抵触しないとして、被告の主張を退けた。
地裁は、物質特許を採用しない理由を、物質に特許が与えられると、その物質の発明者にあらゆる用途、あらゆる製法を支配する強力な独占的効力を持つ物質特許を付与してしまい、他人がその物質についてより優れた製造方法の発明をなす事を奨励し期待することが困難になるからであるとした。このような法意に基づけば、物質特許禁止の規定からは、新規物質の製法特許の保護範囲の認定につき一般の場合と異なった限定的解釈を取らなければならない理由は生じないと解している。そして、このことは、均等論の適用の妥当性の裏付けの一つとなっている。
高裁の判決文を見る限り、本件特許の出願時に物質特許が禁止されていたことなどの状況は、考慮されておらず、化学物質を直接的には保護しないという政策的選択があったことが、高裁の判断に影響を与えたようには見受けられない。
(6)特許請求の範囲おける不必要な限定
優先日当時、特許請求の範囲に記載されたエステル化法、イ号方法に用いられたエステル化法は、それぞれ周知慣用であった。このことは、地裁と高裁の判決文に引用されている、甲第15号証の1から明らかである。イ号方法にせよ特許発明の方法にせよ、化学反応自体は当業者が知っており、目的化合物が与えられれば予測できたものである。
これに対し、特許権者は、ベストモードを開示した。出願当時の知識でも、特許請求の範囲に記載されたハロゲン化物を用いたエステル化法が、一般にもっとも優れたものと信じられており、被告も認めているように、請求の範囲に記載の方法の方が、イ号方法より実際に優れていた。イ号方法は、退歩発明、あるいは改悪であろう。
このように見てくると、出願時の手続きのやり方として、代理人は、エステル化法の詳細を特許請求の範囲に規定せずに、単に、「エステル化法による」といった広い表現を使用するべきであったとも考えられる。
もちろんそのためには、酸クロライド法、ハロゲン化アルキルアミン法(本件特許)のほかに、エステル交換法、アミノ基置換法、カルボン酸法(イ号方法)、酸無水物法、その他を可能な限り網羅して明細書に記載すべきであったろう。
しかし、これは物質特許が認められていたとすれば、不必要な記載である。現在日本を含む主要国で適用されている審査基準によれば、新規物質の製造方法は少なくとも一つ記載されていればよいこととされているからである。
物質特許が認められていた外国での出願をそれが禁止されていた日本に持ち込むときに、どこまで明細書を手直しすべきか、どこまで出願人にそのような記載の負担を求めるべきかというのは、国際的な制度調和の面から考える必要がある。単に日本の法制及び判例の独自性をいって、この問題を看過することはできない。本件は、物質特許を禁止していた出願当時の法制により、相当な不利を被った事例であると考えられる。
(7)平成10年2月最高裁の均等論判決に鑑みて
平成10年2月24日に、最高裁判所は、いわゆる「スプラインボール軸受け事件」(平成6年(オ)第1083号)において、均等論を再定義する判決を出した。この判決によれば、特段の条件を満たさなくても、文言通りの侵害がないイ号製品または方法が特許発明の技術的範囲にはいるかの判断を行うことができる。その意味で、本判決は、均等論のより積極的な適用に道を開くものである。
このことを、メクロフェノキセート事件の高裁判決を維持した最高裁の態度が、均等論をより積極的に支持する方向へと変化したものと評価することも可能ではあろう。ただし、高裁判決においては、均等論に否定的な見方をとっているものの、置換可能性や置換容易性の一応の判断はなされているので、事実認定の正誤を検討しない最高裁判所としては、均等論に対する考え方の如何を問うても、高裁判決を覆すことは難しかったのも事実であろう。
最高裁判所が今回示した均等の要件として一般的に重要な点としては、三点ある。一つは、いわゆる置換容易性が「対象製品等の製造等の時点において」判断されるとした点、もう一つは、「対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではな」いこと、そして、「対象製品等が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情もない」ことである。これらは、最近の判例に鑑みて、決して全く新しい要件であるとはいえないものの、最高裁判所が、これらをいわゆる「均等」の定義としたことの意義は大きい。
これらを本件の塩酸メクロフェノキセート事件に当てはめて考えると、地裁判決および高裁判決のいずれにおいても、優先日を置換の「容易性」の判断日として考えている。しかし、判断時を侵害時としても、侵害を認めた本事件の地裁の判決は言うに及ばず、高裁の判決の理由ならびに結論も変化していたとは考えられない。これは、上述のように、高裁判決においては、本件特許発明の目的、課題を、イ号方法の工業的な実施の可能性の探求に置き替えていることから、その枠組みにおいては、イ号方法と特許発明方法の差異は、侵害時においても、置換容易とならないからである。
さらに、今回の最高裁判決においては、いわゆる自由技術の抗弁、出願経過禁反言としてそれぞれ知られていた考え方が、均等の要件に明示的に組み入れられている。本件特許発明にかかる物質、すなわち侵害品は、出願日の公知物質ではなく、また、先行技術から容易なものであったわけではない。本件においては特許性の有無は争われておらず、物質特許がなかった時代に、化学的類似方法の特許として、製法の対象物の新規性と進歩性を基礎に、その製法に対して特許がなされていた当時においては、特許性を争わずして、自由技術の抗弁は成り立ち得なかったであろう。また、地裁と高裁の判決文による限りにおいて、出願経過禁反言の適用を受けるべき、すなわち、「出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外された」と考えるべき事実はない。本件特許は、訂正審判によりその範囲が限定されているが、出発物質、すなわち目的物質を限定するものであり、請求の範囲に記載の化学反応方法自体を限定したものではない。
5.まとめ
委員会の検討の中でも、特に化学系の専門家の意見としては、エステル化の反応がありふれたものであることもあり、一審判決に対する賛意が強かった。
判決の結論をさておいても、制度的、技術的な実体から、均等論に関する本件の事案を判断しようとする大阪地裁の態度には、共感できる部分が多い。上述のように、現在の通説的な均等論判断の手順を必ずしも厳密に踏んでいるわけではないが、本件の大阪地裁判決は均等論のあり方について有益な示唆が多い。
![]()